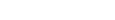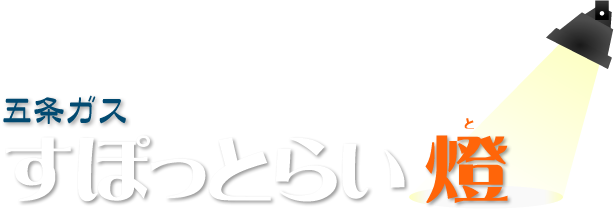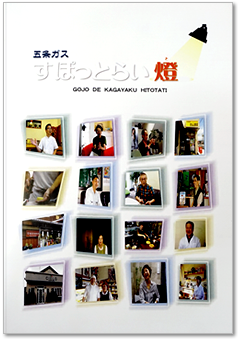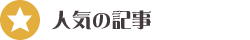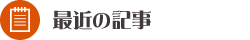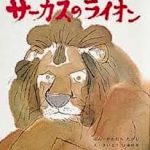見えない何かに引っ張られてる気がして

30年の長い眠りから目覚めようとする藤岡家。かつての偉人の家を蘇らせようと船出します。積まれた宝の存在を知らぬまま進み出した船は、驚き、発見、忍耐、不安、感動・・・と、まさに航海そのもの。さてどうなるのでしょうか。
びっくり! と えらいこっちゃ・・・。
―藤岡家がこのように公開されるようになった経緯について教えていただけますか?
覚えてる方も多いと思いますが、平成10年の台風です。神社の木もなぎ倒されたりと多くの被害が出る中、ここは幸い屋根で済んだといえば済んだんですけど、瓦や煙出しが飛ばされ、ひどい雨漏りで、ご当主が慌てて帰ってこられました。応急処置で屋根にブルーシートをかけ、さてこれからどうしようということになりました。ご当主は「これまで管理は近くに住む方々にお願いしてきた。でもこんな状況のまま迷惑をかけてはいけない」と、この家の今後の何かヒントや答えが見つかればとネット検索したところ「山本本家(五條市の酒造)」さんのページにたどりつき相談します。山本さんは五條で一番最初にインターネットを始めたり、五條のまちおこしをされてきた方で、相談内容から長和と山本さんのお父様がロータリークラブでお知り合いだったことも判り、すぐに五條市役所に繋いでくださいました。
話が進む中、「修理は全て私が(ご当主)がしますから、建物は市に寄付したい」と申し出られるんですが、他にもたくさん古い建物がある五條市がこの先それらを全て管理するのかという意見もあり、市への寄付のお話は進みませんでした。
―市への寄付が叶わず、その後、どうなったんでしょうか?
天誅組関連の町おこしもされてた田中修司さん(㈱柿の葉すし本舗たなか創業者 以下 田中さん)が、藤岡家に天誅組三総裁の一人である松本奎堂が書いた額があるという情報をきっかけにここを訪れます。鑑定の結果、松本奎堂のものではなかったんですが、このお屋敷の立派さに「保存の価値がある」と、田中さんはその後も行政や地域の方、そして私の父(児童文学作家 川村たかし)にもお声がけいただき再び藤岡家を訪れます。私は当時、父の運転手で同行してたんですが、ご当主を交えた話し合い等も重ねた結果、田中さんがこの建物をみんなが集まり食事や談話ができる場所として活用しようという提案をしてくださいました。ご当主も活用してもらえるならと修理してくださることになり、その時は、誰もここにたくさんの貴重なものが眠っているとは知らずに船出するわけです。
―ご当主も貴重な資料などの存在を知らなかったんでしょうか?
ご当主は「当家に残る文化を地域の文化のために活用してください」と明言しておられました。
―川村さんがこちらの館長となられた経緯は?
田中さんが、父の書いた『新十津川物語』などに深く興味をもって下さっていたことから、地域おこしと文学の結びつきに着目なさったのだと思います。以来、土地に残るストーリーを五條の将来への発展に結びつけたいと思っています。
―田中さんがここを訪れたとき、お目当てのものが天誅組関連ではなかったところで終わらなかったことが今に繋がってますね。
そうなんです。こちらのお話を田中さんからいただいたときに父に相談すると「私は14歳の頃に玉骨先生のところに俳句を習いに行ってたから、それはもうぜひ行ってお手伝いしてきなさい」って言うんです。 横で聞いてた母も「お父さん、玉骨先生から「玉蝶(ぎょくちょう)」って俳号もらってるねん」って言うんです。そんな話、初めて聞いたんですよね。「玉蝶って」・・・、父のお酒のアテを作ったりしながら「お父さん、文学って何ですか」って恐る恐る話しかけてた怖い父と「蝶」というイメージがつながらなくて(笑)
―藤岡家での最初の「お宝発見」はどんなものだったんですか?

母屋で資料整理をしている時、柱時計の下を通りかかった棟梁の柴田正輝さん(以下 棟梁)が「これメイドインUSAって知ってるか?」って言うんです。おばあちゃん家にあったような時計だと特に気に留めてなかったんですが、振り子箱を開けて見てみると、江戸末期頃のアメリカ、セス・トーマス社製の時計(米国でも最古の時計)だったんです。もうびっくりして。その時ですね、もしかしたら、ここはすごいお家かもしれんって思ったのは。

棟梁が率いる修理工事の方達が、「川村さん、色々出てくる。まず何が必要や?」て聞いてくれて、「どうも、ここは『大坂屋』という屋号みたいなので、『大坂屋』と書いてるものがあったらとにかくそれをください」って言いましたら、次来た時には色々机の上に置いてくれてあるんです。母屋や米倉に使われていた鉄釘1本も大切に「この鉄釘が貴重やった」と。この建物、建築に対するリスペクトがあり、昔の建築の素晴らしいところを崩さず、できるだけ残そうと、各分野の職人さん達が協力し3年半かかって修理してくださいました。
―開館に向けて最初にした「お仕事」は何ですか?
「玉骨句集」のデータ化です。玉骨は俳人として有名だったのに句集を1冊しか出してないんです。その句集もたった1冊しか残っていませんでした。これをまずデータとして保存しなければとコピーを持ち帰り子供が寝た後、作業をする訳ですが・・・、えらいこっちゃです。難しいんです!(笑)
昭和33年に出た句集なら私と同い年、大丈夫だわ・・・と、偉そうに持ち帰ったものの上質で非常に難解な俳句ばかりでした。
―どういう俳句だったのでしょうか?
小さな命をものすごく大事に、子供や鳥、虫の様子、命を詠む句がたくさんあるんですね。敗戦後、五條で俳句を教えながら静かに暮らして、大勢のお弟子さんがいながら結社も立ち上げないし句集も1冊しか出さない。目立たずとにかく人を育てようとしていたのがわかりました。私の父が児童文学を始めたきっかけは昭和30年代、小学校教師だった父は「子供の読むもの」がないって思ったらしいんです。童謡や昔話はありましたが、「児童文学」というジャンルはその頃まだ育ってなかったんですね。
父は「児童文学は3歳の子供でも80歳の方が読んでも同じように価値があるもの。世代を超えて全ての人に伝えられる、新しい時代を作る子供達の児童文学を書きたい」と思い始めるんです。そのとき父が言った「子供は未来やから」っていう言葉が子供ながらに、すごいこと言うなって思ってたんです。文化が充実し生活が豊かになることで相手を思いやる心や、戦わずに問題を解決する力が養われる、そのためのエネルギーは未来をつくる子供達の教育だということを、父はここにきて玉骨先生から学んだんじゃないかと思いました。
スターバックスで噴き出してしまって
―長い修理期間を経ていよいよ開館。当日はどんな様子でしたか?またその後の反響はどうだったんでしょうか?
平成20年11月11日、11時11分開館のセレモニーは、華やかで、テープカットもあり多くの人やテレビ局、新聞社が来られました。お神楽やお琴、藤岡家のご親戚のシャンソン歌手奥田真祐美さんの歌の披露がありました。12月まで無料ご招待で大勢の方がお越しくださり、年明けからの有料入館では年間12,000人の方が来てくださいました。梅を見に、お雛様を見に、先のお客様をご案内して戻るともう次のグループが待ってる・・・みたいな状態。田中さんが工夫を凝らしたお料理や地域のお店の出張ランチなど、1日100人の入館、というような日も時にはありました。
―華々しいオープニングとその後も盛況だったんですね。
はい。でも、いざ入館料を頂戴するとなったら果たして皆さん来てくださるのかというのは実はすごく心配でした。「お食事処」とは別に私は「見てもらう部分」を作る立場だったので大丈夫かな・・・って。そしたら、10時頃坂道を登ってくるひとりの男性がいらして、どうも雰囲気的にこちらに向かってるんです。セーターを着て飄々と歩いて来られて、通り過ぎずに入口に向かって曲がってくれたときは心の中で「やった!有料入館第一号のお客様が来てくれた」と思いました。その方はなんと、阿波野青畝(奈良県高取の俳人 以下 阿波野青畝)先生の長男、阿波野健次さんだったんです。こんな方が第一号で来てくれるというのは、これから「俳句の館」という方向で進むのかなとも感じました。
―これまで行われた企画などをご紹介いただけますか?
五條ロータリークラブさん主宰(玉骨は初代ロータリークラブ会長)で「子供俳句教室」をずっとしています。子供達は上辻先生(奈良県俳句協会理事)に俳句を教えてもらう前に、私が「誰でも上手になれる俳句」っていうのを教えるんですけれど、もうね、子供達の俳句が素晴らしくて。子供ならではの視点というか、大人が助言していたらちょっと違ったものになると思うんですが、子供独自の目線でこそ詠める句だなっていうのが寄せられてくるんです。こんな素晴らしい句が詠める子供達が五條の未来にあると思うと嬉しくて。ただ問題は「誰でも上手になれる」ので私が追い抜かれそうなこと(笑) ここがほんと問題(笑) 今は五條東小学校の子供さんに参加してもらってるんですけど、私の望みは五條市の全小学生に俳句を教えさせてもらうこと。これは野望です(笑)
―川村さんはいつから俳句を始めたんですか?
開館のときに何を展示するか・・・で、私はちょうどその年、生誕1000年と世間で話題になっていた「源氏物語」をしたいと言ったんです。与謝野晶子直筆の「源氏物語礼讃歌」っていう長い巻物があって、これこそ開館記念展示にふさわしい資料と思ったんです。でも上辻先生が「いや最初は俳句や」っておっしゃるんです。確かに立派な俳人たちの短冊はたくさんありましたが、私は「俳句より与謝野晶子や源氏物語の方が有名やん」と内心思ったんです。ですが、「ここには俳句の世界ではびっくりするような方々の短冊が残されてるんやからやっぱり最初は俳句」と決まりました。それでもまだ「何で・・・」と思うほど俳句を分かってなかったんです。
先生方のおっしゃる通り、俳句で大勢の方が来てくださいました。となると、私もこれから短冊を詠めないといけないんですよね。阿波野青畝の短冊はめちゃめちゃあるし、加えて、青畝のお弟子さんからの短冊や本が寄付されてくるんです。「阿波野青畝展」をすることになり、「阿波野青畝句集」をちゃんと読み始めたんです。そしたら、句の中に画像がいきいきと浮かんできます。橿原のスターバックスで読んでいて、とうとう噴き出してしまいました。
―句集で噴き出したとはどういうことでしょうか?
一見ぶっきらぼうな句などがあります。青畝は耳がご不自由なのですが、聞こえないというご自身の辛さを高いところから俯瞰して笑ってしまっている。すごいなって思いました。句の中に「おかしみ」があります。心の辛さや困難なことが、俳句で客観写生することによって笑いに変わっているのですね。『枕草子』の「いとおかし」の境地にも届く深さがあります。そこからです。俳句を勉強しようと思ったのは。
―川村さんは俳誌「ホトトギス」の同人ですね。
はい。普通ならどこか結社に入らせてもらったらいいんですけど、そうすると吟行や俳句会に出席しないといけないんです。となると仕事があるし子供もいるし、父母の手伝い等もあって時間的にとても無理なのでNHKの俳句添削講座を始めました。右も左もわからないままのスタートでしたが、ひとつの自信は玉骨句集のデータ化と阿波野青畝句集や、後藤夜半らの句集などの読み込みでした。もしかしたら何とかなるかなと。それで2年間くらい添削を続けて、ある程度見えてきたところで、すごいハードルは高かったですが、思い切って「ホトトギス」にと投句したら稲畑汀子先生(虚子の孫)の「天地有情」にまず一句が掲載されたんです。もう嬉しくて!小さい字だったんですけど、ここに持ってきてみんなに「見て見て!」って言ってね。こんなの一生に一回かもしれないと思いました。その後主宰の稲畑浩太郎先生選の「雑詠」に毎号載るようになり、その後も投句をずっと続けてたら何年か前に「左の人を同人に推薦します」ってとこに私の名前があって!もうこんな嬉しかったことはなかったですね。
―その後の藤岡家はどのように進んできたのでしょうか?
田中さんの構想でたくさんの方にここを知ってもらうことができましたが、その後、田中さんが御年齢の事もあってキッチンを辞められます。開館から1~2年は月に1回のランチサロンやお琴の会など地元のいろんなものを生かしてイベントを行っていましたが、徐々に、厨房スタッフの常駐、お客様が来られなかった場合の食材の廃棄の問題等、色々な意見が出てきました。そしてコロナ禍の時代が来て、飲食を中止しました。
―美味しいものと見学するもの、どちらもあるのは魅力ですが、運営側としてはそういった事情もおありだったのですね。
田中さんが退かれ厨房の方も一旦休止し、今後どういった運営をしていくかというお話で、ご当主がおっしゃったのは「自分が英国などに行くと古いお家のものをいっぱい資料として展示しているところがあり、それは次の文化にとって、ものすごい力になっている。外国を旅した時にそれを強く感じる。英国なんかは入館料も結構高い。これからもしかしたらここも入館料を値上げすることになるかもしれないけれど、もっと資料に特化してもいいんじゃないでしょうか」ということでした。ほっとしたというのが正直な気持ちでした。その後、天誅組関連やたくさんの資料がどんどん出てきて、いろんな展示もさせていただいてきましたが、この先、ここをどうしていくのか、どうなっていくのか。進む方向はこのお家を守ってこられたご先祖様が決めてくれるでしょうって、私はどこか気楽に思っています。でも精一杯の努力は日々続けています。
―進んでみてわかることもありますものね。
こんな素敵なところでいただく季節の料理。すごい楽しい時間でしたね。「地域を大事に、みんなが楽しめる場所」っていうのは田中さんから学びましたし、ご当主は今も、維持管理費をずっと送ってくださってます。「いつもありがとうございます」とメールすると、「ありがとうはいらないですよ」って。
―台風被害の後、取り壊されてもおかしくないはず。ご当主が「修理、保存」という選択肢をお持ちだったこと、そして山本さんのHPにたどりついた奇遇など、藤岡家の船出は導かれてたんですね。
ほんとにそうです。ご当主は「更地にしようかとも思った」とおっしゃってました。先代当主も同じご意見だったそうですが、最終的な判断はご当主に委ねられたそうです。ご当主のお考えと、山本さんや田中さんはじめ、五條を引っ張ってきてくれた方々が集まって力を貸してくださいました。藤岡家住宅の開館は、五條ロータリークラブの発足50周年の記念でもあり、クラブの方も邸内に句碑を建立してくれたり、俳句会の開催をご支援くださるなどご尽力くださっています。